舗装は水と温度にきわめて敏感です。
無理に施工すれば、剥離・わだち・空隙増大などの不具合を招き、品質は取り戻せません。
さらに、散布した乳剤が舗装面から流出して構造物を汚損したり、河川・田畑の用水へ流れ込めば、環境負荷だけでなく多額の補償や信用の失墜につながります。
工程が厳しい時ほど、「やる/やらない」の見極めは慎重に。
品質・安全・信頼を守るのは、監督の判断です。
本記事では、現場で即決できるNO-GO/GOの基準と手順を整理しました
(最終判断は仕様書および発注者の指示を優先してください)。
NO-GO(中止すべき条件)
- 路面に水膜・水たまりが残る、または降雨が継続見込み。
- 下層(路床・路盤)が含水過多でわだち・泥濘がある。
- タックコートが乾かない/接着面が濡れている。
- 合材・マットの必要温度が確保できない(規定未満の恐れ)。
- 交通開放までに品質・安全が確保できない(視界不良・滑走リスク)。
GO(実施可とする最低条件と対策)
- 雨が止み、表面水がない。水切り後にエアブロー・ワイパで乾燥を確認。
- 降雨は一時的で、短時間に仕上げられる範囲へ施工規模を縮小できる。
- 先行排水(側溝掃除・排水誘導)、タック完全乾燥後に敷均し。
- 合材温度・マット温度・ローラーパスを確保し、転圧時間短縮の段取り(機械配置・人員増)をとる。
- 必要に応じて簡易屋形・シートで局所養生、合材の待機ロスを最小化。
判断フロー(現場即決用)
- 気象確認:雨雲レーダー・降雨予報・現地雨量。
- 現地確認:表面水/下層含水/接着面の乾燥。
- 代替工程:路盤整正・側溝・付帯工への切替を検討。
- 合意化:発注者・元請・プラントと「GO/NO-GO」を共有。
- 記録:判断理由(天気・写真・温度・雨量・対策)を日報に残す。
ポイント(若手向けメモ)
- 迷ったら中止案を第一候補。品質は取り戻せない。
- プラント発注は「GO合図」後、便を細かく分けてロスを回避。
- 中止時は即リスケ(交通誘導・機械・運搬の再手配)までやり切る。
まとめ
水・温度・時間の3点が揃わなければやらない。
揃える段取りを作れた時だけ、範囲を絞って安全第一で実施する——これが雨天時の王道判断です。
この記事が役に立った、面白かったと思ったら、「現場監督虎の巻」カテゴリをぜひチェックしてくださいね!


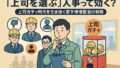
コメント