現場監督の皆さま、お疲れさまです。
法面の安定性を確保するために設けられる「小段排水工」は、雨水や地下水を効率よく排出する重要な構造物です。
しかし、排水機能をきちんと発揮させるためには、設計通りの精度で施工しなければなりません。施工不良は法面崩壊や浸食の原因にもなりかねません。
この記事では、小段排水工の施工で押さえておくべき重要ポイントを、事前準備から完成後の確認まで体系的に解説します。
事前調査と設計照合
設計図と現況の確認:
小段排水工の位置・高さ・勾配が設計図書と整合しているかを確認します。特に排水勾配(通常1~2%)と段の水平性が重要です。
現場の地形や整地状況とのズレがないか、事前に測量で把握しましょう。
法面の安定性評価:
施工箇所が既に安定しているかを確認します。
崩壊の恐れがある場合は、先に法面保護工や仮設足場の設置を検討してください。雨天明けや粘性土層では特に注意が必要です。
施工計画と準備
施工手順の共有:
作業班に対して、小段排水工の構造・寸法・勾配・接続条件について事前に周知し、作業手順や注意点を共有しておきます。
資機材・型枠の確認:
現場で使用する型枠・アンカー・止水材・ベント管などの資材が設計仕様を満たしているかをチェックし、搬入・保管状態にも配慮しましょう。
施工時のポイント
排水勾配の確保:
水が滞留しないよう、排水路の勾配は常に設計通りに確保します。
丁張りやレベル測量を活用しながら、高さ管理を徹底してください。
継手部・接続部の処理:
既設の側溝や集水桝などとの接続部では、水密性を確保するために止水材の適切な設置と充填確認を行い、漏水防止を図ります。
鉄筋・コンクリート打設:
鉄筋が設計通りに組まれているか、かぶり厚さを確保しているかを確認しましょう。
打設時はジャンカ防止や締固めに留意し、表面仕上げも丁寧に行います。
完成後の点検・記録
寸法・勾配の確認:
完成後に再度勾配や寸法を確認し、水たまりや段差、目違いがないかを目視および測量でチェックします。
施工記録の整理:
写真・チェックリスト・レベル記録などを活用して、施工状況を記録に残しましょう。後の維持管理やトラブル対応に役立ちます。
まとめ
小段排水工の施工は、法面の安全性や周辺構造物への影響を左右する重要な工程です。
設計照合・勾配管理・水密処理・施工記録という一連のプロセスを丁寧に進めることで、品質の高い仕上がりが実現します。
この記事で紹介したチェックポイントを、ぜひ現場標準のルールとして活用し、信頼される施工管理を目指してください。
この記事が役立ったら、ぜひ「現場監督虎の巻」カテゴリもご覧ください!


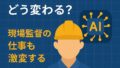
コメント