現場監督の皆さま、こんにちは。
工事着手前に必ず行う「現場踏査」は、設計図書と実際の現場を突き合わせる重要なステップです。
「図面を見ながら歩くだけ」と思われるかもしれませんが、地形や地質、既存構造物、周辺環境などの“現実”を把握しないと、その後の施工計画に大きなズレやトラブルを招きます。
以下では、現場踏査で特に押さえておきたい10のポイントを解説します。
①設計図書との徹底した照合作業
- 図面に示された寸法・位置・構造が現場と一致しているか確認する。
- 図面だけでは分かりにくい部分や不明確な表示がないかチェック。
- 差異があれば写真やメモで記録し、速やかに監督職員に報告・協議する。
②工事区域と仮設工事用地の把握
- 契約で定められた本体工事範囲(工事区域)を正確に確認。
- 現場事務所、作業員宿舎、資材置き場など仮設工事に必要な用地を把握。
③地形・地盤・湧水の状況確認
- 地形の凹凸、地盤の硬軟、岩盤の有無を目視でチェック。
- 湧水の有無・量を確認し、排水対策の要否を判断。
- 地質調査報告書と照合し、軟弱地盤や支持力不足のリスクを把握。
④周辺環境と公衆災害防止
- 周辺の既存構造物への振動・騒音・粉じん等の影響を検討。
- 第三者の立ち入り禁止措置や標識設置など、安全巡視計画への反映。
⑤地下埋設物・架空線の徹底調査
- 水道・ガス・電気・通信などの埋設管・ケーブル位置を把握し、管理者へ照会。
- 必要に応じて試掘を実施し、その結果を監督職員へ報告。
⑥施工上の制約条件の洗い出し
- 作業スペースや重機搬入の可否を確認。
- 交通規制が必要な箇所・時間帯、河川工事の水切り条件、出水期・降雪期などの制約を把握。
- 関係機関や地元との協議事項を明確にする。
⑦資材・建設機械の適合性確認
- 設計指定の資材や建設機械が手配可能かを確認。
- 代替機械の使用が望ましい場合は監督職員に承諾を得る。
- 資材保管場所として適切な用地を確保。
⑧工程計画の基礎情報収集
- 地形・地盤・制約条件をもとに、作業順序や各工程の所要時間を検討。
- 準備期間や片付け期間を含めた全体工程をイメージし、ネック作業を洗い出す。
⑨人員計画の基礎情報収集
- 必要な技能や資格を持つ作業員の人数を見積もり、確保見通しを立てる。
⑩必要書類作成のための資料収集
- 踏査で得た情報を施工計画書や報告書、写真管理に活用。
- 図面と異なる箇所は写真撮影・詳細メモを徹底し、後日の説明資料とする。
監督職員との緊密な連携が成功の鍵
踏査で見つけた異常や疑問点は、必ず自己判断せず監督職員に報告・相談してください。
報告・通知・協議・承諾など、契約図書に定められた手続きを書面(工事打合せ簿など)で行うことが基本です。
また、発注者・受注者・設計担当者が集まる三者施工協議会の機会があれば、積極的に参加して設計意図を理解しましょう。
まとめ
工事着手前の現場踏査は、その後の工事品質・安全性・工程・コストに直結する重要な業務です。
本記事で紹介した10のポイントを踏まえ、設計図書と現場のズレを徹底的に確認し、監督職員と密なコミュニケーションを図りながら、安全・円滑な工事開始を目指しましょう。
この記事が役立ったら、ぜひ「現場監督虎の巻」カテゴリもご覧ください!

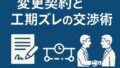

コメント