はじめに
現場監督の皆さん、日々の業務お疲れ様です!
特に若手の皆さんは、覚えることが山のようにあって大変ですよね。その中でも「施工検討会」は、打ち合わせの数だけ面倒に感じるかもしれません。
しかし、この場をしっかり活用することで、工事の手戻りやトラブルを大幅に減らし、品質や安全を確保できます。
施工検討会とは?
施工検討会は、現場代理人、主任技術者、専門技術者、監督職員など関係者が集まり、設計図書の読み合わせや施工方法の詰め、品質・安全・環境対策の確認を効率的に行う場です。
他にも、発注者や自治体など外部との承認事項をまとめる重要な機会でもあります。
なぜ施工検討会が重要なのか?
- ① 設計図書の早期照査
設計図に潜む誤り・不一致を全員で洗い出し、疑義点は監督職員とすぐ協議。手戻りや追加費用を防げます。 - ② 現実的な施工計画の策定
施工計画書案をベースに、材料保管方法や建設発生土の処理、安全/環境対策などを具体化し、実行性を高めます。 - ③ 想定外トラブルへの備え
地質や埋設物など予期せぬ現場変化を想定し、迅速な対応フロー(監督職員への連絡含む)を共有します。 - ④ 品質・出来形管理の確認
コンクリート試験や寸法測定など、どのタイミングで何を検査するかを決め、役割分担も明確化します。 - ⑤ 関係者間の合意形成
発注者・下請け・協力会社・官庁など、多様なステークホルダーと情報を共有し、承認/協議事項を一元管理します。
若手現場監督へのアドバイス
- 事前準備を徹底
配布資料(図面・仕様書・計画書案など)には必ず目を通し、疑問点や確認事項をリストアップ。 - 積極的に質問
分からないことは恥ずかしがらずに発言。先輩や監督職員の意見は自分の財産になります。 - 議事録で記録・共有
決定事項や保留点は必ず書面に残し、関係者全員に配布して情報の抜け漏れを防ぎましょう。 - フォローアップ
検討会で決まった内容は現場に落とし込み、進捗確認ミーティングで常に見直しを。
まとめ
施工検討会は、設計図書の正確な理解、現実的な施工計画の立案、予期せぬトラブルへの備え、品質管理の徹底、関係者間の合意形成という五つの要を一度にクリアできる貴重な場です。
若手現場監督の皆さんには、ぜひ積極的に参加し、工事を成功へと導くスキルを磨いてほしいと思います。
頑張ってください!応援しています。
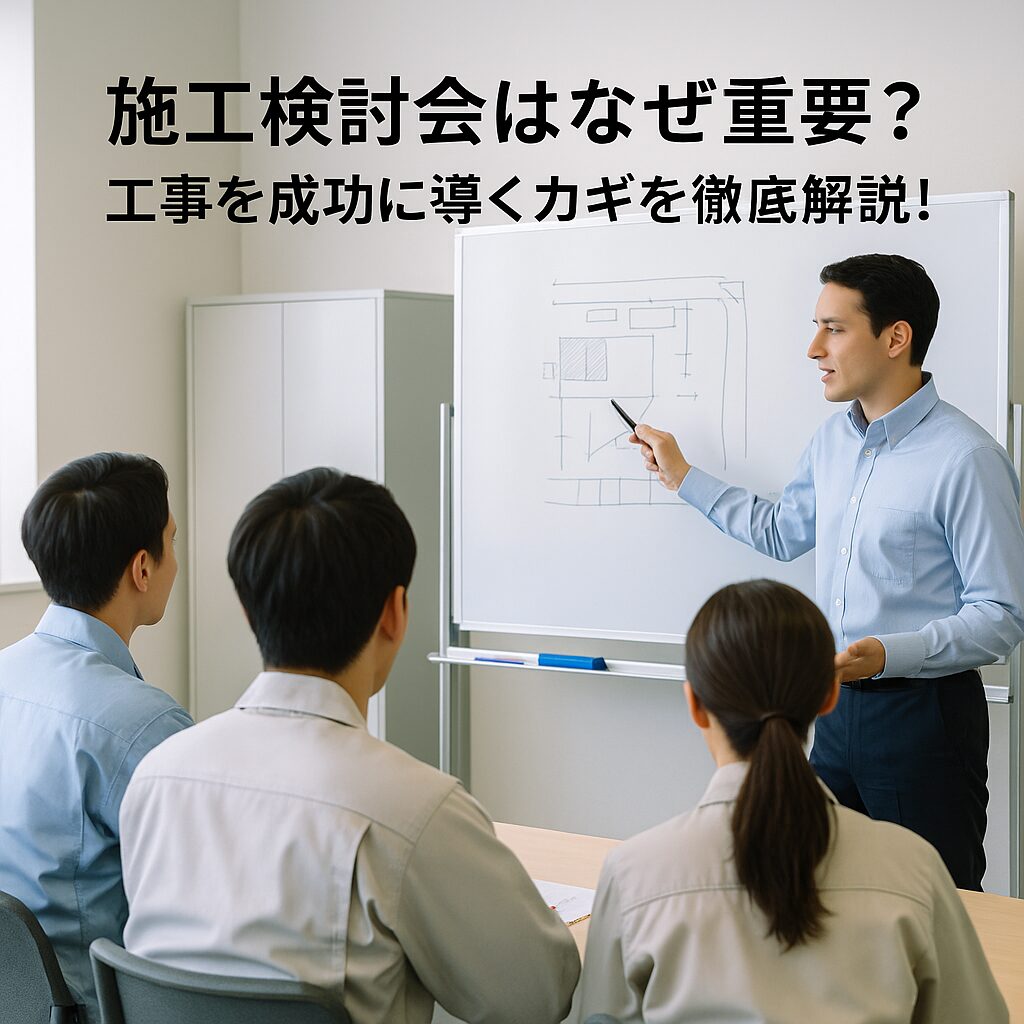


コメント